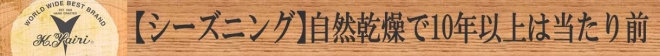ギタリストでなくてもその名を耳にしたこともあるであろう「K.Yairi」。
ミュージシャンからの絶大な信頼を得る「Yairi」ブランドのギターを製作するヤイリギターに潜入取材!
今回は、ゼネラルマネージャーの矢入賀光(ヨシミツ)氏に工場内をくまなくご案内いただきました。
ヤイリギターの工場内、回ってみると本当に興味深い!
さっそく工場内へ一緒に向かいましょ〜
ヤイリギター潜入開始!

こちらも手作りでしょうか。
かわいらしい看板が出迎えてくれました。

まずはロビーへ。
さっそくユニークなギターたちが目に飛び込んできます。

あ! 弦剣だ!
ロビーで「お掛けください」と引かれた椅子はなんと、ヤイリギターの職人お手製の椅子!
Yairiロゴマークにくり抜かれた背もたれは、ギターの形です!!

座らせて頂いても落ち着きませんw
だって周囲に面白そうなものがたくさんあるんですもの。
この壁も何やら見た事のあるような、ないような木材ですね…

「あ、その壁? 指板ですよ♪」
えぇ!?
確かに良く見るとローズウッドっぽい。
目を凝らしてみるとこんな感じの穴が…

「木材って、ギターに使えないものもあるんです」
「その穴は自然乾燥中に虫に食われた跡(笑)」
「もったいないから壁材に使ってます」
さすが日本でも有数の木材備蓄量を誇るギターメーカー…
楽器に使用できなくとも無駄にしないわけですね。
木材ストック〜乾燥
ヤイリギターには、今この瞬間から木材を買わなくても、およそ10年間はギターを作り続ける事が出来るだけのストックを持っています。

ヤイリギターの倉庫は風通しが良くなっていて、

こんな感じで、同じ方向に桟(サン)積みされています。(これはTOP材ですね)
それによって木材と木材の間に風が通って、乾燥されていきます。
なんと、ヤイリギターの自然乾燥は少なくとも10年は自然乾燥させるそうです。
昭和末期から積んである物もあります!!(奥の方だったので撮影できませんでした…)
画像は平成15年の12月に積み上げたという記述が。それでもすでの10年弱経過してます!
これ、桟積みするのに相当時間かかるし、かなり難しい作業らしいです。
積んでる間に横に曲がっていってしまうので、しっかり積むのにも熟練の技が必要ですね。

積み上げが美しい!
自然乾燥中にもこうやって木材が動いて、反る物も出ます。

最終的に、調整してギターに使えるかどうかを判断します。
ネック材は、ある程度製剤された状態でヤイリギターに入荷します。

かなり大まかですが、すでにネックの形をしています。

桟済みされる前のTOP材。
けっこうな厚みです。
ここから削っていって、TOP材の厚みになっていきます。


50~60℃の温度で1週間〜10日間くらい乾燥させるそうです。

ちなみに含水率は最終的に10〜12%くらいまで落ちます。
自然乾燥の最後の仕上げ的な作業です。
製品として出回るギターも8%くらいまで落ちているので、購入後の乾燥は必要以上にやらないで下さい、との事です。
※乾燥させすぎれば、やはり割れが出ます。適度な水分も必要なのです。

強制乾燥が終わった物や、ある程度整形されたものがしっかり湿度管理されて保管されています。

あ、よだれが…(笑)

ちなみにヤイリギターでは、ラミネート材を安くて悪い材とは考えていません。
熱を加えて反らせるときに、単板だとやはり弱いので、あえて合板を使う、
またエレアコは、ハウリング防止の為にサイドとバックは合板にする、
などといった使い方をします。

アーティスト用エレアコのサイドとバックは基本的に合板がほとんどだそうです!

島村楽器のコラボレーションモデルの材もしっかりストックされています。

あれ? 食堂にステージが…?

社員の方はもちろん、アーティストの方もここに来て演奏を披露されるそうです。
食堂を歩いていると、ふと矢入氏、
…え!?
導管に水分が入らないように目止めをして、ネジでいつでも外せるようになっているそうです。
ちょっとしたシーズニング(笑)
味噌汁をこぼしたりして、適度な水分になるのでしょう…
年輪ごとに歴史的出来事が書かれた年表が貼られています。
この木が生まれたのは「関ヶ原の戦い」の年!

実際にTOP材として使うのはこの部分。
(え? これしか使えないの!?)

古い部分は堅すぎるし、若い部分はコシが無い。
けっこうギターに使える部分って少ないんですね。
そりゃあ、個体差が出るわけです。

ギターを選ぶ楽しさってこういう所からも伺い知れますね。